嫌なことを言われても気にしない方法ができる人には、共通して“やらない”思考習慣があります。
日常生活や職場、SNSなど、私たちはさまざまな場所で心ない言葉にさらされることがありますが、そんな中でも心を乱されずにいられる人たちは、何を考え、どう行動しているのでしょうか。
本記事では、嫌な発言を受け流すための心の持ち方から、冷静な対応術、習慣的に取り入れたい行動までを解説します。他人の評価や否定に振り回されず、自分らしく毎日を過ごしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
嫌な言葉への心構えや受け流す思考法が学べる
他人の発言を冷静に受け止めるための技術がわかる
自分軸を育てて評価依存から抜け出す方法が理解できる
嫌な出来事を成長のチャンスに変える発想が身につく
嫌なことを言われても気にしない方法と心の守り方
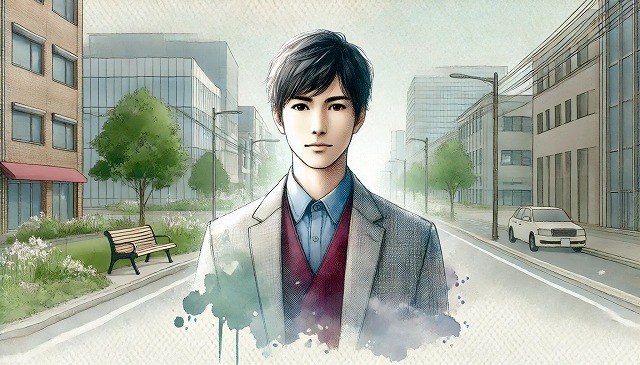
私たちは日々、様々な人と関わりながら生きています。その中で、心ない言葉や否定的な意見に傷ついたり、落ち込んだりすることは誰にでもある経験でしょう。しかし、そうした言葉に過度に振り回されず、自分の心を健やかに保つことは可能です。このセクションでは、まず心の内面や考え方からアプローチし、嫌なことを言われても気にしないための「心の守り方」を解説します。
嫌な思いをしないためにはどうしたらいいですか?
完全に嫌な思いを避けることは難しいかもしれませんが、事前に心構えをしておくこと、そして物事の捉え方を変えることで、ダメージを最小限に抑えることは可能です。
- 嫌なことが起きる前の「心構え」と予防法 世の中には様々な価値観を持つ人がおり、時には自分とは合わない意見や、配慮に欠ける言葉を発する人もいるという現実を受け入れましょう。「誰もが自分を理解し、好意的に接してくれるわけではない」と理解しておくだけで、予期せぬ言葉に対する心の準備ができます。また、普段から自分の意見を穏やかに伝える練習をしておくことも、一方的に嫌なことを言われる状況を防ぐ一助となります。
- 相手の言葉を”鵜呑みにしない”思考のクセづけ 誰かから言われた言葉を、そのまま「事実」や「絶対的な評価」として受け止める必要はありません。それはあくまで「その人のフィルターを通した意見の一つ」に過ぎないと考えるクセをつけましょう。「この人は今、こういう視点で物事を見ているんだな」「何か背景があるのかもしれない」と一歩引いて考えることで、言葉の重みを軽減できます。
- 「その人の問題」と切り分ける意識の持ち方 相手が嫌な言葉を発する背景には、その人自身のストレス、コンプレックス、価値観、あるいは単なる虫の居所が悪いといった、「相手側の事情」が大きく関わっていることが少なくありません。アドラー心理学でいう「課題の分離」のように、それは「相手の問題」であり、あなたが背負うべき「あなたの問題」ではない、と切り分ける意識を持つことが大切です。相手の機嫌や価値観と、あなた自身の価値は全く別のものです。
何を言われても気にしない方法
実際に嫌なことを言われたとき、どうすれば心を波立たせずにいられるのでしょうか。ここでは、具体的なメンタル術とトレーニング方法をご紹介します。
- どんな言葉にも過剰反応しないメンタル術 カチンときたり、深く傷ついたりした時こそ、感情的に即座に反応しないことが重要です。まずは深呼吸をするなどして、一呼吸置きましょう。相手の言葉を冷静に受け止め、「事実」と「意見」、「感情」を分けて考える練習をします。感情的になっていると感じたら、その場を少し離れるのも有効です。
- 感情と現実を切り離すトレーニング 嫌なことを言われたという「現実(出来事)」と、それによって引き起こされる「自分の感情(怒り、悲しみなど)」は、本来別のものであると認識するトレーニングです。「〜と言われたから、私は〜と感じている」と客観的に分析します。感情は出来事によって自動的に決まるのではなく、自分の受け止め方次第で変えられる、という意識を持つことが大切です。
- アサーティブな自己防衛の基本 もし、相手の言葉が明らかに間違っていたり、不当だと感じたりした場合は、自分を守るための自己主張も必要です。ただし、攻撃的になるのではなく、「アサーティブ」に伝えることを意識しましょう。アサーティブ・コミュニケーションとは、相手を尊重しつつ、自分の気持ちや考えを正直に、誠実に伝える方法です。「私は(その言葉を聞いて)〜と感じました」のように、”I”(私)を主語にして伝える(アイメッセージ)のが基本です。
スルースキルが高い人の特徴は?
嫌なことを言われても上手に受け流せる「スルースキル」。このスキルが高い人には、どのような特徴があるのでしょうか。
- 高いスルースキルを持つ人の思考習慣・行動傾向 スルースキルが高い人は、物事を客観的に捉える能力に長けています。自分と他人との間に適切な境界線を引くことができ、他人の問題を自分の問題と混同しません。感情のコントロールがうまく、必要以上に反応せず、冷静さを保てます。また、話題を転換したり、ユーモアで返したりするなど、その場を和ませるスキルを持っていることもあります。
- 反応しない=「鈍感」ではないことの説明 スルースキルと聞くと、「鈍感」「無神経」といったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、それは誤解です。スルースキルは、何も感じないことではなく、感じた上で「どのように反応するかを選択できる」能力です。感受性は豊かでも、ネガティブな感情に振り回されず、自分を守るための知恵と言えるでしょう。
- 誰でもできる”スルースキルの育て方”紹介 スルースキルは、意識と練習によって誰でも高めることができます。まずは、日常生活の中の小さな「嫌なこと」から受け流す練習をしてみましょう。「これは自分の問題ではない」「この人の機嫌の問題だ」と心の中で唱えるだけでも効果があります。また、瞑想やヨガなどで心を落ち着ける習慣を取り入れることも、感情の波に飲まれにくくなるために役立ちます。
いちいち気にしない名言
時には、偉人や著名人の言葉が、心を軽くし、強くしてくれることがあります。
- 世界・日本の偉人や著名人による「心を強くする言葉」紹介
- 「他人が自分のことをどう考えているかなど、気にする必要はない。彼らはそんなにあなたのことを考えている暇はないのだから。」(エレノア・ルーズベルト)
- 「幸せかどうかは、自分の心が決める。」(相田みつを)
- 「たとえ全世界が敵になっても、自分だけは自分の味方でいなさい。」(デール・カーネギー)
- (その他、ガンジー、マザー・テレサ、スティーブ・ジョブズなどの言葉も有効)
- 名言の背景と、なぜ心が軽くなるのかを解説 これらの名言が心に響くのは、人生の普遍的な真理や、困難を乗り越えてきた人々の経験に基づいているからです。他人の評価軸ではなく、自分自身の内面に目を向けることの大切さ、物事の捉え方次第で現実は変わることなどを教えてくれます。共感や新たな視点を与えてくれることで、悩んでいた心がふっと軽くなるのです。
- 名言を”使いこなす”方法(ノートに書く、唱える等) 心に響いた名言は、ただ読むだけでなく、積極的に活用しましょう。お気に入りの言葉を手帳やノートに書き留める、スマートフォンの壁紙にする、鏡の前で声に出して唱えるなど、日常的に触れる機会を作ることで、その言葉が持つ力がより深く心に浸透していきます。辛い時や落ち込んだ時に、それらの言葉を思い出すことで、心の支えとなるでしょう。
嫌なことを言われたらチャンス
一見ネガティブに思える「嫌な言葉」も、捉え方次第では自分を成長させるチャンスに変えることができます。
- 嫌な言葉を「学び」として捉えるマインドセット 言われたこと全てを真に受ける必要はありませんが、「もしかしたら、自分では気づかなかった改善点や、成長のヒントが含まれているかもしれない」という視点を持つことも大切です。まるで自分を磨いてくれる「紙やすり」のように、厳しい言葉が自己成長のきっかけになることもあります。
- フィードバックの視点で見ることで成長に変える 感情的な部分や、明らかに的外れな部分は受け流しつつ、「客観的なフィードバック」として捉えられる部分がないか探してみましょう。例えば、仕事の進め方やコミュニケーション方法について、具体的な指摘があれば、それは改善のチャンスかもしれません。ただし、あくまでも「参考意見」として、取り入れるかどうかは自分で判断することが重要です。
- 実際のシーン別”チャンス変換術”【例:職場・家族】
- 職場: 上司や同僚からの厳しい指摘 → 「期待の裏返し?」「もっと効率的な方法があるかも?」と考え、具体的な業務改善のヒントを探る。
- 家族: 価値観の異なる意見 → 「こういう考え方もあるのか」「なぜそう思うのだろう?」と相手を理解しようと努め、コミュニケーションを深めるきっかけにする。
嫌なことを言われても気にしない方法と習慣づくり
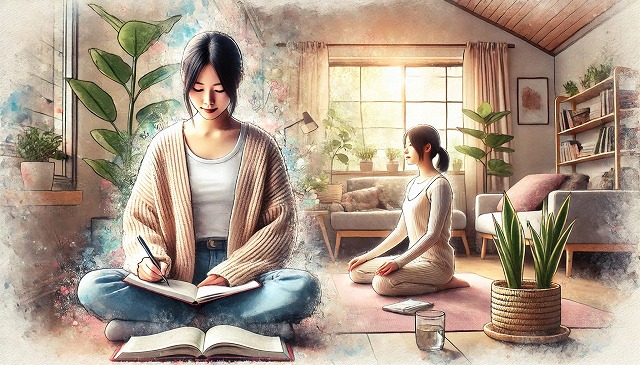
心の持ち方を変えるだけでなく、日々の行動や習慣を見直すことでも、嫌なことに動じない強い心を育てることができます。ここでは、具体的な習慣づくりの方法を見ていきましょう。
人にどう思われても気にしない方法
「他人にどう思われているか」を過剰に気にしてしまうのはなぜでしょうか。その心理背景を知り、評価依存から抜け出すステップをご紹介します。
- 「他人の目線」を気にしすぎる心理の背景 他人の評価を過度に気にする背景には、誰かに認められたいという「承認欲求」の強さ、自分に自信がない「自己肯定感の低さ」、過去に否定されたり、仲間外れにされたりした経験などが関係していることがあります。
- SNS・職場・学校など”評価依存”からの脱却法 「いいね!」の数やフォロワー数、周囲からの評判ばかりを気にする「評価依存」から抜け出すためには、まず、そうした評価システムとの距離を意識的に取ることが有効です。SNSを見る時間を減らす、リアルな人間関係や自分の感覚を大切にするなどが考えられます。
- 自分軸を育てる3ステップ(自己理解・決断・発信) 他人の評価に振り回されない「自分軸」を育てるには、以下のステップが有効です。
- 自己理解: 自分が本当に好きなこと、大切にしたい価値観、譲れないことは何かを深く知る。
- 決断: 他人の意見に流されるのではなく、自分の価値観に基づいて物事を判断し、決断する経験を積む。
- 発信(表現): 小さなことからで良いので、自分の考えや好きなことを表現する機会を持つ。服装や持ち物で個性を出す、自分の意見を言ってみるなど。
実は嫌われてる人の特徴は?
もし、あなたが頻繁に周りから嫌なことを言われると感じているなら、無意識のうちに人を遠ざけるような言動をしてしまっている可能性も考えてみる価値はあるかもしれません。
- 無意識に人を遠ざけてしまう言動・口癖 例えば、常に否定的・批判的な発言が多い、自分の話ばかりで人の話を聞かない、自慢話が多い、平気で悪口や陰口を言う、時間にルーズ、感謝や謝罪の言葉がない、などの言動は、無意識のうちに周囲の人を不快にさせ、距離を置かれてしまう原因になり得ます。
- 周囲に嫌なことを言われやすい人の共通点 一方で、自己主張が極端に苦手だったり、何でも「いいよ」と断れなかったり、感情を溜め込みやすかったりする人も、相手につけこまれたり、ストレスのはけ口にされたりして、結果的に嫌なことを言われやすい傾向があるかもしれません。
- 変えられるポイントを見極めて改善する視点 もし、自分の言動に思い当たる節があれば、それを客観的に見つめ直すことが第一歩です。信頼できる友人や家族に、「自分の言動で気になるところはないか」と正直に聞いてみるのも良いでしょう。全てを完璧に変える必要はありませんが、改善できるポイントを見つけ、少しずつ意識して変えていくことで、人間関係が良い方向に変わる可能性があります。
嫌なことを完全に忘れる方法はありますか?
一度言われた嫌な言葉が、いつまでも頭の中で繰り返されてしまう…そんな辛い経験から解放されたいと思うのは自然なことです。完全に記憶を消すことはできませんが、その影響を和らげる方法はあります。
- 嫌な記憶を脳内で整理する「忘却テクニック」 人間の脳は、ネガティブな出来事を記憶しやすい性質を持っていますが、その記憶に囚われ続けないための工夫は可能です。完全に忘れるというよりは、「思い出す頻度を減らす」「思い出しても感情的な影響を受けにくくする」ことを目指します。
- 書き出し・言語化による”感情の外在化” 頭の中でぐるぐる考えてしまう思考を止めるには、「外に出す」ことが有効です。言われて嫌だったこと、その時の感情、思ったことなどを、誰にも見せないノートに自由に書き出してみましょう。また、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうことも、感情を整理し、客観的な視点を得る助けになります。
- 寝る前のリセット法/瞑想・運動・音楽などの活用 嫌なことを考えがちな夜は特に、意識的にリセットする時間を作りましょう。寝る前に軽いストレッチや瞑想をする、好きな音楽を聴いてリラックスする、日中に適度な運動をして心地よい疲労感を得る、趣味に没頭する時間を作るなど、自分に合った方法で気分転換を図ることが大切です。
嫌なこと言われた時の返し方
どうしてもその場で何か対応しなければならない状況や、自分の尊厳を守るために反論したい場合もあるでしょう。ここでは、角を立てずに、かつ自分を守るためのスマートな返し方をご紹介します。
- その場で冷静に返す”神対応フレーズ” 感情的にならず、冷静に対応するためのフレーズ例です。
- 「そうなんですね。」(一旦、相手の言葉を受け止める姿勢を示す)
- 「そういう考え方もあるんですね。」(同意はせず、意見の一つとして認識)
- 「貴重なご意見ありがとうございます。」(丁寧に対応し、議論を深入りさせない)
- 「(少し考えて)〇〇ということでしょうか?」(相手の意図を確認し、時間稼ぎと冷静さを保つ)
- 「そう言われると、私は少し悲しい(残念な)気持ちになります。」(アイメッセージで自分の感情を伝える)
- 攻撃を避けつつ自己主張を伝える会話術 相手の土俵に乗って感情的に言い返すのではなく、あくまで冷静に、事実と自分の意見・感情を分けて伝えることを意識します。相手の人格を否定するのではなく、「その発言」に対してどう感じたかを伝えます。ユーモアを交えたり、話題を変えたりして、深刻な対立を避けるのも有効な場合があります。
- 後からじわじわ効く「反論しない反撃法」 その場で言い返さなくても、自分を守る方法はあります。
- 沈黙: あえて何も言わずに相手を見つめることで、相手に自分の発言を考えさせる。
- 場を離れる: 「少し頭を冷やしてきます」などと言って、物理的に距離を取る。
- 記録する: いつ、誰に、何を言われたかを記録しておく(特にハラスメントの場合)。
- 気にしない態度: 相手の言葉に全く動じない態度を示すことが、ある意味で最も効果的な「反撃」になることもあります。
嫌なことを言われても気にしないためには、心の持ち方を変えること、そして具体的な行動や習慣を身につけることの両方が大切です。すぐに完璧にできるようになる必要はありません。少しずつ、自分に合った方法を取り入れながら、しなやかで強い心を育てていきましょう。この記事が、あなたの心が少しでも軽くなるための一助となれば幸いです。
嫌なことを言われても気にしない方法のまとめ
嫌な言葉を避けるには、他人の価値観に過度な期待をしない心構えが有効
相手の発言は「一意見」と捉え、鵜呑みにしない習慣をつける
嫌な発言は「相手の問題」と切り分けて受け止める意識が大切
感情と出来事を分けて考えることで心のダメージを軽減できる
アサーティブな伝え方で自分を守る主張力を育てる
スルースキルは「鈍感さ」ではなく、反応を選ぶ知恵である
偉人の名言を活用することで、心の支えと視点の転換が可能
嫌なことを「成長のきっかけ」として捉える柔軟な発想が有効
SNSや他人の評価から距離を取り、自分軸を育てることが重要
自分の言動を見直し、無意識の言動が原因になっていないか確認する
嫌な記憶の影響を減らすには、感情を言語化して外に出すことが効果的
嫌な発言への返し方には、冷静さとユーモアを交えた対応が有効

コメント