その場しのぎの嘘をつく人は、無意識のうちに自分を守ろうとする心理が働いていることがあります。この記事では、そうした嘘の原因や背景を解説しながら、改善するための方法や周囲の適切な対応について詳しく紹介しています。虚言癖との違いや、発達障害・パーソナリティ障害といった関連する特性にも触れながら、本人の心理や行動の傾向を理解し、信頼関係を築くための対処法を解説しています。嘘に悩む人も、その周囲の人も参考になる内容です。
その場しのぎの嘘をつく人の心理や原因が理解できる
虚言癖や発達障害などとの違いが把握できる
嘘を改善するための具体的な方法がわかる
周囲の人が取るべき適切な対応や伝え方が学べる
その場しのぎの嘘をつく人の治し方とは
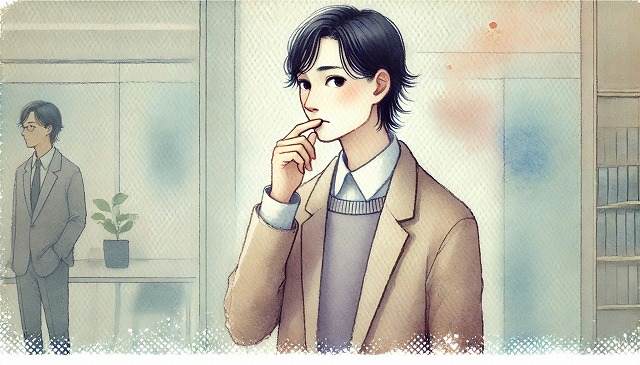
虚言癖の人に見られる共通パターンとは?
なぜ平気で嘘がつけるのか?その心理を深掘り
自分を守るために嘘をつく人の本音とは?
怒られるのが怖くて嘘をつく大人たちの実態
思わず嘘をつく人の特徴とは?その場しのぎの裏側に迫る
その場しのぎの嘘は、計画的なものではなく、反射的に出てしまうことが多いのが特徴です。まるで「癖」のように、困難な状況や気まずい場面に直面すると、深く考えずに嘘をついてしまいます。
- とにかく「今」を乗り切る思考: 将来的に嘘がバレて困る可能性よりも、「この瞬間をどう切り抜けるか」が最優先されます。後先考えずに、その場を取り繕うための言葉を選んでしまうのです。
- 罪悪感の薄さと一貫性のなさ: 嘘をつくことへの罪悪感が比較的薄い傾向があります。そのため、以前の発言と矛盾するようなことを平気で言ったり、話の辻褄が合わなくなったりすることも少なくありません。
- 自分を守りたい気持ちの表れ: 多くの場合、失敗を隠したい、怒られたくない、相手の評価を下げたくないといった自己防衛的な心理が働いています。)
- 見た目や話し方の傾向: 特に決まった見た目の特徴はありませんが、咄嗟に嘘をつく際に、目が泳いだり、早口になったり、逆に不自然に落ち着いた態度を取ろうとしたりするなど、無意識のサインが現れることもあります。
虚言癖の人に見られる共通パターンとは?
その場しのぎの嘘が癖になっている状態と似ていますが、「虚言癖」はより深刻な問題を抱えている場合があります。
- 日常的に嘘を繰り返す「慢性型」: 虚言癖の人は、特定の状況だけでなく、日常的に嘘をつくことが習慣化しています。本人も嘘をついている自覚がありながら、やめられないケースが多いです。
- 現実と空想の混同: 自分のついた嘘を真実だと思い込んだり、現実と空想の区別がつきにくくなったりするタイプもいます。話を大きく盛ったり、全くの作り話をしたりすることも特徴です。
- 背景にある心理: 強い承認欲求や低い自己肯定感が背景にあることが多いです。自分を実際よりも良く見せたい、注目されたい、現実の自分から逃避したいといった気持ちが、嘘を繰り返させる原因となります。
- その場しのぎ型との違い: その場しのぎの嘘は、主に「困難な状況回避」が目的ですが、虚言癖は「自己顕示欲」や「現実逃避」など、より根深い心理が動機となっている点が異なります。また、虚言癖は本人が嘘を信じ込んでいる場合がある点も違いと言えます。
なぜ平気で嘘がつけるのか?その心理を深掘り
「どうしてあんなに平気で嘘がつけるんだろう?」と疑問に思うかもしれません。その心理にはいくつかのタイプがあります。
- 良心の呵責が薄いタイプ: 嘘をつくことに対する罪悪感や、他人に迷惑をかけることへの意識が低い場合があります。自分の行動が他者に与える影響をあまり考えない傾向が見られます。
- 他人を操作・支配するための嘘: 自分の思い通りに他人を動かしたり、状況をコントロールしたりするために、意図的に嘘を使う人もいます。これは反社会性パーソナリティ障害の特徴として見られることもあります。
- 共感性や道徳観念の欠如: 他人の気持ちを理解したり、社会的なルールや道徳を守ったりすることへの意識が低い場合、平気で嘘をつく行動につながることがあります。
- パーソナリティの問題: 上記のような特徴が顕著な場合、単なる性格の問題ではなく、パーソナリティ障害(例:妄想性、反社会性、演技性など)が背景にある可能性も考えられます。
自分を守るために嘘をつく人の本音とは?
その場しのぎの嘘の多くは、「自分を守りたい」という心理が根底にあります。
- 評価を下げたくない・非難されたくない: 失敗やミスを正直に話すことで、自分の評価が下がったり、他人から非難されたりすることを極端に恐れています。嘘をつくことで、そうしたネガティブな状況を避けようとします。
- 責任を負いたくない: 自分の言動の結果として生じる責任を回避したいという気持ちも、嘘をつく動機になります。面倒なことや不利益を被ることを避けたいのです。
- 相手の反応への過度な恐れ: 相手がどう反応するか、特に怒られたり、失望されたりすることを過度に恐れている傾向があります。相手の機嫌を損ねないように、つい嘘をついてしまうのです。
- 根底にある「防衛本能」: つまり、その場しのぎの嘘は、自分自身の心や立場を守るための「防衛本能」の一種と捉えることができます。本能的な反応であるため、なかなかやめるのが難しい側面があります。
怒られるのが怖くて嘘をつく大人たちの実態
特に「怒られること」への恐怖心が強い人は、その場しのぎの嘘をつきやすい傾向があります。
- 子ども時代の体験の影響: 子どもの頃に、親や教師から過度に厳しく叱られたり、高圧的な態度を取られたりした経験がトラウマとなり、大人になっても「怒られること=怖いこと」という認識が強く残っているケースがあります。
- 「怒られる=拒絶される」という思考: 怒られることを、単なる注意や指導ではなく、自分自身の存在を否定されたり、拒絶されたりすることだと感じてしまう思考の癖があります。
- 様々な場面での実例: 職場でのミスを隠す、家庭でパートナーに都合の悪いことを言えない、恋愛関係で相手に嫌われないように本心を偽るなど、様々な場面でこのパターンが見られます。
- 対話における「安心感」の重要性: このタイプの人に対しては、頭ごなしに叱ったり、問い詰めたりするのではなく、「責めない」「話を聞く」という安心感のある態度で接することが、正直なコミュニケーションを促す鍵となります。
その場しのぎの嘘をつく人の治し方実践術
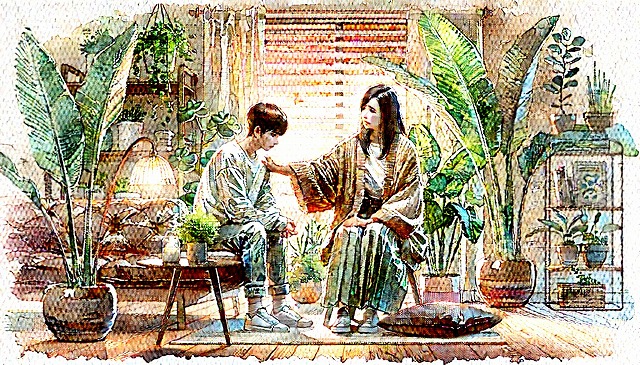
嘘をつく人の「育ち」と環境の関係とは?
平気で嘘をつく人の裏に潜むパーソナリティ障害
女性に多い”嘘のクセ”とその背景を読み解く
その場しのぎの嘘と病気の関係を正しく理解する
嘘つきの心に届く言葉、どう伝える?
嘘を指摘したり、改善を促したりする際には、伝え方が非常に重要です。相手を追い詰めず、心に響くコミュニケーションを心がけましょう。
- 相手のプライドを守る: 真っ向から「嘘つき!」と決めつけるのではなく、「もしかして、こうだったんじゃない?」など、相手の逃げ道を残しつつ、事実確認をするような言い方を工夫します。
- ポジティブな表現を使う: 「本当のことを話してくれて嬉しい」「正直に言ってくれてありがとう」といった肯定的な言葉は、相手に安心感を与え、正直であることのメリットを感じさせます。
- 直接否定しないテクニック: 「そういうことにしておくね」と一旦受け止める姿勢を見せたり、「知っている人に確認してみるね」と間接的に嘘に気づいていることを示唆したりするのも有効です。
- 信頼関係を大切にする: 嘘を責めることよりも、なぜ嘘をつく必要があったのか、その背景にある気持ちを理解しようと努めることが、信頼関係を維持・再構築するために重要です。
嘘をつく人の「育ち」と環境の関係とは?
その場しのぎの嘘をつく癖の背景には、育った環境が影響している場合があります。
- 厳しい家庭環境の影響: 親からの過干渉や過度な期待、日常的な叱責や否定的な言葉が多い環境で育つと、「正直に話すと怒られる」「良い子でいないと認めてもらえない」と感じ、嘘をつくことでしか自分を守れない、あるいは親の期待に応えられないと思い込んでしまうことがあります。
- 「嘘でしか自分を守れない」という学習: 嘘をつくことで怒られずに済んだり、その場を乗り切れたりした経験が積み重なると、「嘘は有効な手段だ」と学習してしまい、癖になってしまうことがあります。
- 自己肯定感の欠如と回復: こうした環境は自己肯定感の低下を招きやすく、それが嘘をつく原因にもなります。回復のためには、ありのままの自分を受け入れ、小さな成功体験を重ねて自信を取り戻していくことが大切です。カウンセリングなども有効な手段となります。
- 生育環境と”嘘の癖”の因果関係: 必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありませんが、生育環境が嘘をつく行動パターンに影響を与えている可能性を理解することは、本人や周囲の人が問題を捉え直す上で役立ちます。
平気で嘘をつく人の裏に潜むパーソナリティ障害
その場しのぎの嘘とは異なり、あまりにも平然と、あるいは悪意を持って嘘をつく場合、パーソナリティ障害が隠れている可能性も考慮する必要があります。
- 関連するパーソナリティ特性:
- 演技性パーソナリティ障害: 注目を集めるためなら、話を大げさにしたり、嘘をついたりすることを厭わない傾向があります。
- 反社会性パーソナリティ障害: 他人の権利や感情を軽視し、自分の利益のために嘘をついたり、人を騙したりすることに罪悪感を感じにくい特徴があります。
- 妄想性パーソナリティ障害: 他人に対する不信感が強く、根拠のない疑いを抱き、それを事実かのように話すことがあります。
- 一般的な嘘との違いと対応の難しさ: これらの場合、本人は嘘をついている自覚がなかったり、嘘をつくこと自体が目的になっていたりするため、一般的な嘘への対応が通用しにくいことがあります。
- 診断・治療の選択肢: パーソナリティ障害が疑われる場合は、精神科医や臨床心理士などの専門家による診断が必要です。治療法としては、カウンセリングや精神療法などがあります。
- 対応に必要な「理解」と「距離感」: 周囲の人は、まず専門的な知識に基づいて相手の状態を理解しようと努めることが大切です。その上で、深入りしすぎず、適切な距離感を保つことが、自分自身を守るためにも重要になります。
女性に多い”嘘のクセ”とその背景を読み解く
性別によって嘘のつき方に違いがあるわけではありませんが、社会文化的な背景から、女性に比較的見られやすいとされる「嘘のクセ」もあります。
- 「場の空気を読む」文化の影響: 日本の文化では、特に女性に対して、場の調和を保つことや相手への配慮が求められる場面が多くあります。その結果、本音をそのまま言うのではなく、相手を傷つけないためや、その場の雰囲気を壊さないために、軽い嘘や話を合わせるような言動をとることがあります。
- 共感・配慮型の軽い嘘や脚色: 相手の気持ちに寄り添うあまり、事実を少し脚色したり、共感を示すために本当は思っていないことを言ったりするケースです。悪意があるわけではなく、むしろ優しさや配慮からくる場合が多いです。
- 恋愛、育児、ママ友関係での典型例: パートナーに心配をかけないための嘘、子どもの手前つく嘘、ママ友同士の付き合いを円滑にするための建前などが、具体例として挙げられます。
- 寄り添った接し方が鍵: このタイプの嘘に対しては、頭ごなしに「嘘だ」と指摘するのではなく、なぜそのような表現をしたのか、背景にある気持ち(気遣い、不安など)を理解しようと努め、共感的な態度で接することが、より良い関係性を築く上で大切です。
その場しのぎの嘘と病気の関係を正しく理解する
その場しのぎの嘘が、発達障害やその他の精神疾患と関連している場合もあります。ただし、安易に「病気だから」と決めつけるのは避け、正しい理解が必要です。
- 発達障害(ADHD、ASDなど)との関連:
- 衝動性 (ADHD): よく考えずに反射的に言葉を発してしまい、結果的に嘘のようになってしまうことがあります。
- コミュニケーションの特性 (ASD): 本音と建前の使い分けが苦手だったり、相手の意図を誤解したり、事実の捉え方が独特だったりすることで、意図せず嘘をついているように見えてしまうことがあります。
- 「嘘」ではなく「認知のズレ」の場合も: 発達障害のある人の場合、本人にとっては事実を述べているつもりでも、周囲との認識の違いから「嘘」と捉えられてしまうケースがあります。悪意や欺瞞の意図がないことがほとんどです。
- 精神疾患との線引き: 前述のパーソナリティ障害のほか、うつ病や不安障害などで判断力が低下し、その場しのぎの言動が増えることも考えられます。しかし、単に嘘をつくからといって、すぐに精神疾患と結びつけるのは誤りです。
- 治療よりも支援と理解が重要: 発達障害の特性による「嘘」のように見える言動に対しては、治療というより、本人の特性を理解し、コミュニケーションの方法を工夫したり、安心して過ごせる環境を整えたりする「支援」が重要です。明確な指示やこまめな確認、失敗を責めない姿勢などが有効です。
その場しのぎの嘘に悩んでいる方も、周りの人の嘘に困っている方も、まずはその背景にある心理や原因を理解しようとすることが、解決への第一歩となります。必要であれば、カウンセリングなどの専門家の力も借りながら、より良いコミュニケーションを目指していきましょう。
その場しのぎの嘘をつく人の治し方と向き合い方
その場しのぎの嘘は反射的に出る癖のような行動である
嘘をつく背景には自己防衛や評価を守る心理がある
虚言癖は日常的に嘘を繰り返し、現実と混同する場合もある
嘘をつく人には自己肯定感の低さや承認欲求が関係している
平気で嘘をつける人は共感性や道徳観念が欠如している傾向がある
怒られることへの恐怖心が嘘を生みやすくしている
嘘を指摘する際は、相手のプライドを傷つけない伝え方が重要
嘘の背景には育ちや家庭環境の影響があることも多い
パーソナリティ障害が隠れているケースもあり、専門的対応が必要
発達障害の特性から意図せず嘘になるような言動が出ることがある
嘘と認知のズレを混同せず、冷静な理解が求められる
本人も周囲も、心理的背景を理解し共感的に対応する姿勢が大切である
関連する記事
嘘ばかりつく人の末路とは?信頼を失う人の特徴と心理

コメント